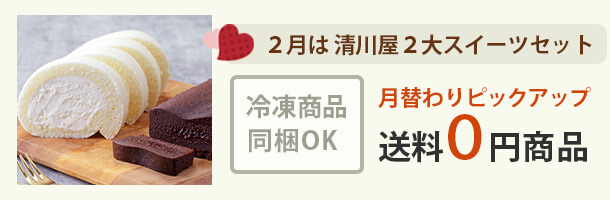気付けば9月も下旬に差し掛かり、やっと秋の涼しさを実感できるようになってきた今日この頃──、そんなときに山形県民が食べたくなるものと言えば、ソウルフードである「芋煮」ですよね♪
9月中旬には「日本一の芋煮会フェスティバル」も無事開催され、清川屋でも材料を煮るだけで簡単に作れる山形のいも煮セットの出荷が始まり、まさしく今が芋煮が美味しく食べられる旬の時期になってきました。
今回は、芋煮に欠かせない野菜・里芋の中でも、鶴岡市の庄内砂丘で育てられている「庄内美人さといも」を栽培する「しじぜんファーム」さんを訪ねました
畑の雑草には意味がある!?冨樫さんの里芋づくりへの情熱

清川屋スタッフたちが訪ねたのは、鶴岡市の西郷地区にある里芋畑。
「しじぜんファーム」さんは小高い砂丘地に広がる畑で、海風が心地よく吹く絶景ポイントに位置しています。
東側には松林の防砂林、北側には鳥海山がくっきり見え、まさに絶景でした!
そんな絶景ポイントで出迎えてくれたのは、「しじぜんファーム」の冨樫英司さん。
農家生まれの冨樫さんは、もともと農業を継ぐ気はなかったそう。一度は電気関係の仕事についたのですが「この仕事をあと20年続けるのは想像できない」と感じ、心機一転、鶴岡市立農業経営者育成学校「SEADS」に入学。農業の道へ進みました。
ご両親も驚かれたそうですが、今ではお父さんと一緒に米や枝豆を、冨樫さん主体で里芋、ミニトマト、さつまいもを栽培しています。

さっそく里芋畑を見せてもらうと……思ったより雑草が多い( ゚Д゚)!
一瞬心配になる清川屋スタッフでしたが、その雑草の多さにもちゃんとした理由が。砂丘地は日差しの照り返しが強く、土の表面が熱くなりすぎることがあります。そこで、あえて雑草を伸ばすことで、その照り返しを和らげる工夫がされています。
また、里芋は同じ場所で長年栽培していると生育が悪くなったり、枯れてしまったりする「連作障害」になりやすく、同じ場所では2年が限界。現在は畑を3区画に分散させながら合計6反の畑で栽培していますが、来年には1町5反まで畑を広げたいとのこと。
猛暑で他の農家の里芋が枯れてしまう中、冨樫さんは毎日この広い畑に通って草・水・肥料の管理を徹底していました。手間を惜しまない冨樫さんの姿勢、感動的です……!
1町5反って何平方メートル?
1町(ちょう)は1ha(ヘクタール)。
1辺が100mの正方形と同じ広さであり、面積にして100m×100m=10,000㎡になります
1反(たん)は、畳600畳分。
1辺が約31.5mの正方形と同じ広さであり、面積にして31.5m×31.5m=約992㎡すなわち1,000㎡くらい。
なので、1町5反は 14961.25㎡ となります。 現在の畑(6反)は5950.42㎡ですね。
あえて砂丘で育ててます。その理由はいったい…?

里芋は粘土質の湿った土地を好むイメージがありますが、冨樫さんはあえて砂地で栽培しています。その理由は「生産性と見た目」にあります。
何でも、粘土質の土地で育てると掘ったときには里芋が泥だらけになり、乾かして泥を落とす作業が大変になります。
ですが、砂地で育てることで、掘ったそばから砂が落ちてくれるので里芋は泥だらけにならず、収穫作業が格段に楽!
また、見た目がきれいなためスーパーでの売れ行きも良いとのこと。
砂地で育った里芋は、水分量が少ないので薫り高く、ホクホクとした食感になるため、ねばりが苦手な方にも食べやすいそうです(*´艸`*)
ですが、やはり里芋にとっては過酷な環境のため、里芋を育てるための種芋だけは水がたっぷりある冨樫さんの田んぼ近くの土で育てています。美味しいお米が育つ田んぼの近くの土ならば、間違いなく栄養満点ですね♪
意外とデリケート!里芋栽培は工夫が盛り沢山

冨樫さんが栽培している「庄内美人さといも」の品種は、色白で肉質が細かく、ねっとりとしたまろやかなぬめりともちもちとした食感が特徴の「大和早生」。
冨樫さんは自家採取(農家さんが育てた野菜から自分で種を採ること)で種芋を育てています。
そして、この里芋を栽培するにあたっても冨樫さんはあらゆる工夫を凝らしています。
春(4〜6月ごろ)は土づくりと肥料投入から始まります。肥料には豚ぷん堆肥、牡蠣殻、鶴岡コンポスト1を使用していて、その中でも牡蠣殻は砂地と同じアルカリ性のため、土壌がアルカリ性に傾き過ぎないように注意しながら行っています。
そのように作られた土に種芋を植えるのですが、今年はなんと冨樫さんとご家族だけで6000株を手植えしたのだとか( ゚Д゚)!
芽が出たら摘心(芽の先端を摘み取ることで、植物の生長を制御し、わき芽の発生を促す栽培技術)を行って味を良くし、10〜11月に収穫するのが一連の流れです。
「コンポスト」とは?
コンポストは微生物の発酵、分解作用により作る堆肥です。
浄化センターの汚水処理の過程で汚泥という有機性廃棄物が残りますが、この汚泥は農作物を成長させる養分を豊富に含んでいます。
鶴岡市では、昭和61年から「鶴岡市コンポストセンター」で汚泥をもみ殻と混ぜて、発酵、分解させ、「鶴岡コンポスト」を生産してきました。
また、夏の時期(7~9月)はひたすら草刈りと水やりが必要なのですが、今年のような猛暑時は自動散水だけでは足りず、スプリンクラーで補水して対応したのだとか。草刈りについても今年は草刈りをあえて少なくするなどの調整をして保水性を高めたり、追加で水やりをしたり小まめな管理が必要でした。
10月中旬から11月にかけて収穫された里芋は冨樫さんの家の近くの倉庫で保管しながら2月頃まで出荷しています。冷蔵庫ではなく倉庫に保管する理由として、なんと里芋は気温が6度以下だと傷んでしまうため、温かい環境で保存することが必要なんです。
芋系の作物はどこに保管してもなんとなく大丈夫そうなイメージがありましたが、意外とデリケートなんですね…!
里芋づくりを通して伝えたい想いと、今後の挑戦は…

最後に、冨樫さんに「里芋づくりを通して伝えたいことは?」とお伺いすると、
「里芋は山形県民にとってなくてはならない作物でありコミュニケーションツールだと思っています。芋煮会というイベントの際には芋煮を通して歴史や文化、地元のかけがえのない仲間との絆を感じてもらえれば作っている励みになります。」
「今後の挑戦してみたいこととしては、まずは農業で生計を立てていくのが目標です。後々ではありますが、農業をベースにしつつも次世代の教育や経験に活かせる事業もやっていきたいです。」
と語ってくれました。
まだ大きな産地とは言えない庄内地方で里芋を育てることによって、庄内の新たな可能性にチャレンジして欲しいですね(*´ω`*)
おまけ:冨樫さんおすすめ!里芋のフライドポテト

冨樫さんに「里芋の一番好きな食べ方は?」とお伺いしたところ、即答で「フライドポテト!」とのこと。これが超おすすめだそうで、作り方もとってもシンプル。
①里芋を茹でて皮をむく(大きめのものは半分か四つ割りに)
②そのまま素揚げするだけ!
③最後に塩をパラっとかければ完成!
実際に作ってみたら、外はカリッと香ばしくて、中はねっとりホクホク。
じゃがいもとはまた違う、里芋ならではの濃厚な旨みがあって、これはクセになる美味しさでした(*^^*)
ぜひご家庭でも試してみてください!